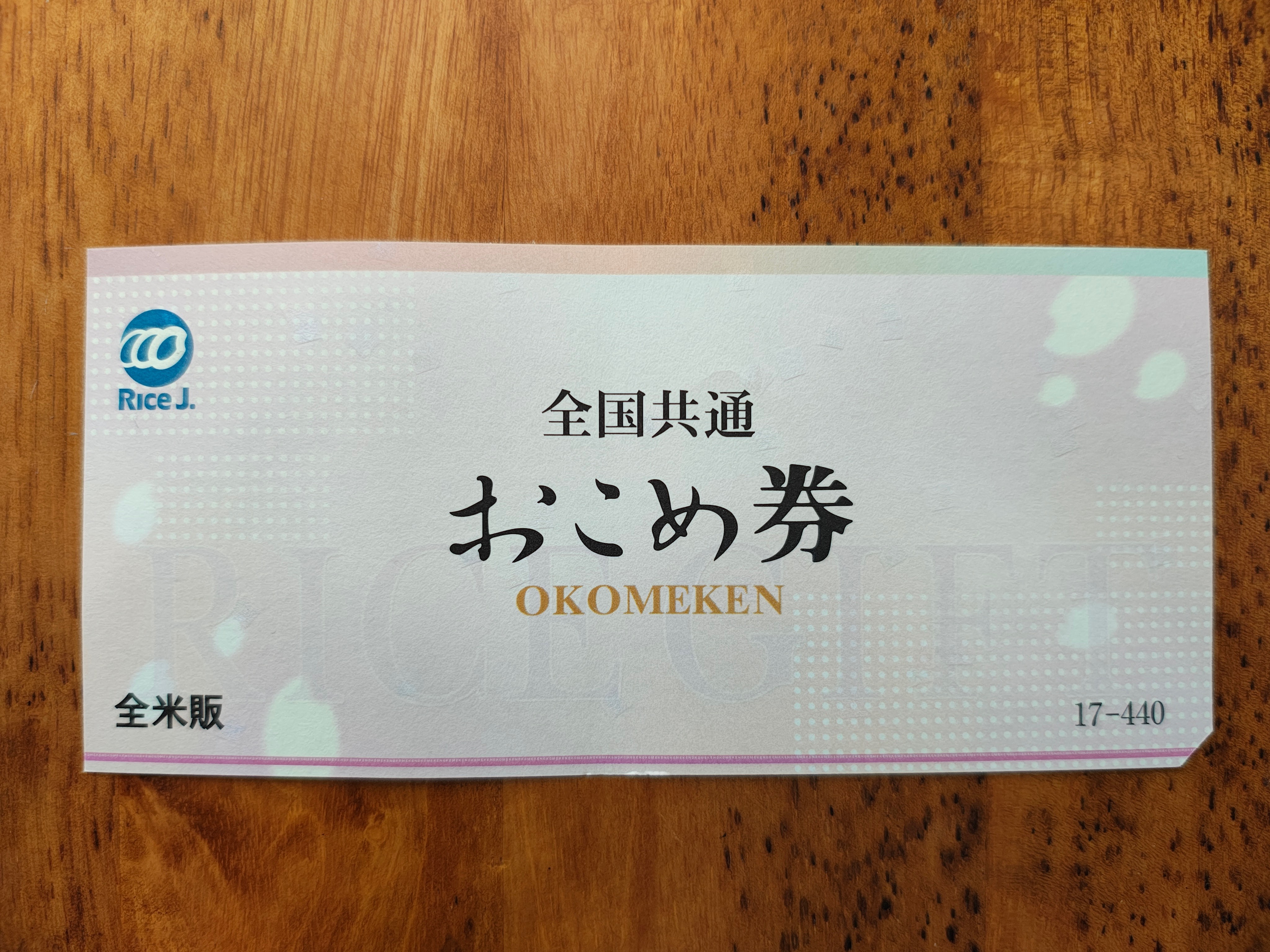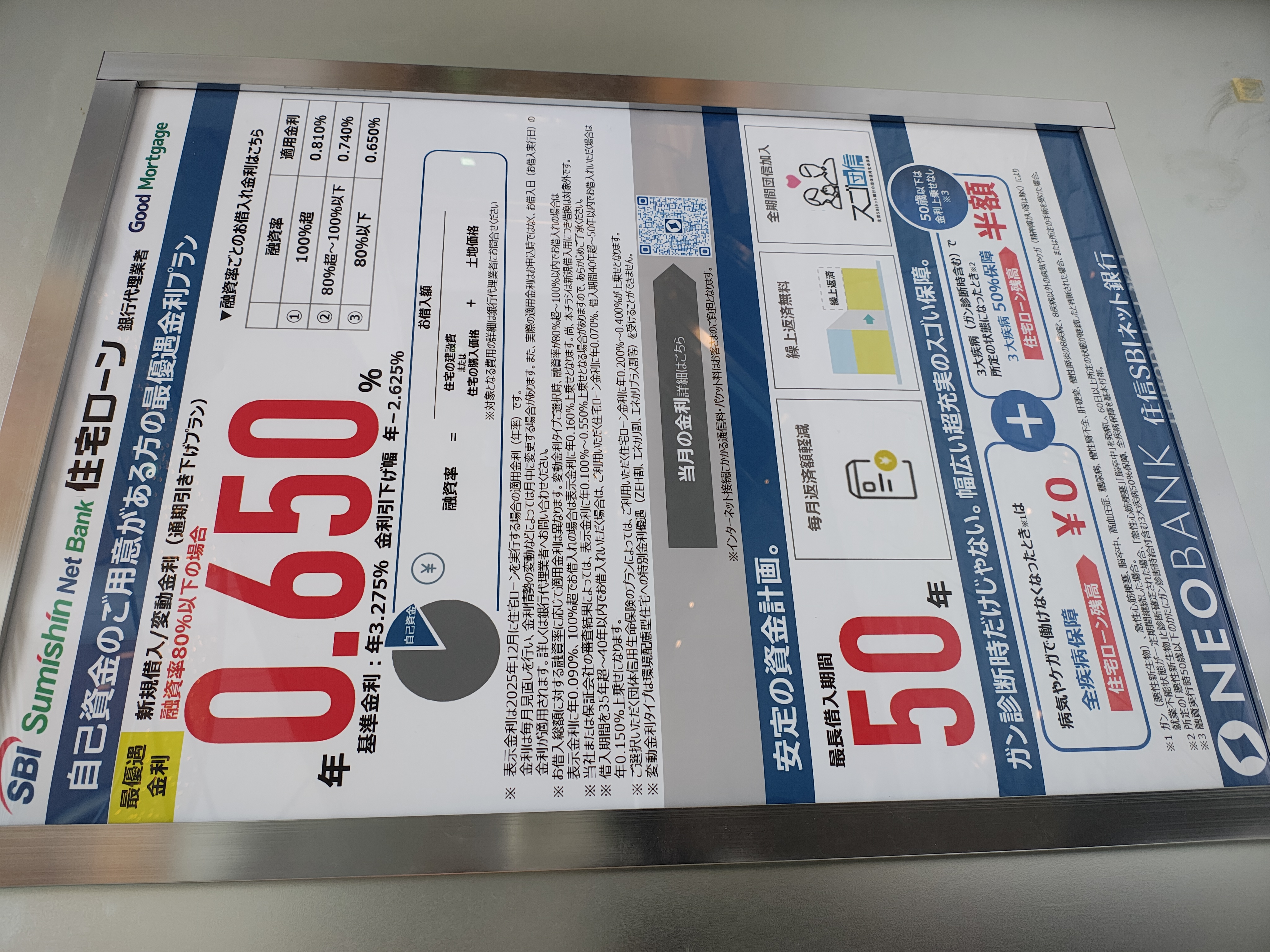家電指定価格制度。
大手メーカーのパナソニックが導入して今春で開始から5年が経過しました。
5年以上経っていますが、家電指定価格制度を知っている人は私の周りでも少なく、殆ど認知されていないように思います。家電指定価格制度を知っている人は日経MJの調査では消費者の16%にとどまり、大手家電量販店7社へのアンケートでは5社が制度には改善すべき点があると感じていました。
「知っている」と答えた消費者の16%のうち「聞いたことがある」程度の人が12%と多く、「簡単な説明が出来る」人は4%と少数でした。
対象拡大を望む家電量販店はゼロで、消費者と家電量販店とメーカーの間で温度差が生じています。
今回は家電指定価格制度について書きたいと思います。

家電指定価格制度とは、メーカー側が家電の販売価格を指示し、どこの店舗で買っても同一商品ならば同一価格になる制度です。
パナソニックが2020年に一部の白物家電で試験導入し、2021年から本格展開を始めました。メーカーが家電量販店からの返品を認める代わりに、メーカーが売れ残りリスクと供給責任を負う仕組みで、家電量販店は売れ残って在庫を抱えるリスクがなくなりました。
一方で家電量販店はメーカーから指定された価格で販売することになり、値引きやポイント付与が自由に出来なくなります。パナソニックに続き、今では日立製作所やロボット掃除機ルンバが有名なアイロボットも導入しています。
パナソニック社長は「家電量販店は在庫リスクを抱える必要がなく、消費者は店を回って価格比較をしたり値引き交渉をしたりする手間がなくなる。『三方良し』を実現出来るスキームだ」と一貫して説明してきました。パナソニックとしても、家電量販店の値引き原資となる販売奨励金が減り、2022〜2023年度は約100億円の営業増益効果がありました。
この制度をパナソニックが導入すると報じられた時は、「メーカーは儲かるだろう」と思いましたが、やはりメーカーは儲かったようです。購入する消費者側としては、どうしても購入価格が高くなりがちだからです。しかしながら、今では家電指定価格制度が話題になることも殆どなく、「そう言えば、そんなこともあったよね」という印象です。
では、家電量販店側はどう受け止めるのか。日経MJのアンケートでは、メーカーへの忖度(そんたく)のない意見を集める為、家電量販店側の会社名が分からないように匿名アンケートにしました。家電量販店の大手7社から回答がありました。
7社の回答は「賛成」0社、「どちらかというと賛成」4社、「どちらかというと反対」2社、「反対」1社と割れましたが、「賛成」は0社でした。「改善すべき点がある」も5社が回答し、パナソニックの制度対象商品の割合を「拡大して欲しい」は0社というアンケート結果でした。
このアンケート結果にパナソニック社長は「(家電量販店側からは)むしろ対象商品の拡大を要求されていると感じていた」と驚いたようです。家電量販店幹部とも頻繁に面会しているとのことでしたが「正面を切って反対された記憶はない」と話し、家電量販店幹部としても正面を切ってメーカーには言いにくい事象のようです。
家電量販店側からの改善要望として多いのは電子商取引(EC)との不公平感です。楽天市場やヤフーショッピングなどのECモールでは、制度対象の家電をポイント付与で実質値下げすることは出来ませんが、複数店舗を買い回ると全体額に対してポイントがたまるキャンペーンを頻繁に実施しています。家電は単価が高いので1%でもポイントが付けば大きく、結婚や就職・進学などの際にまとめて購入した人も多いと思います。
非正規店舗の取り締まりも課題で、制度対象商品は本来は正規店舗以外に出回らない仕組みですが、何らかの裏ルートで一部の対象商品が流通しているようです。メーカーが指定する価格よりも安く出回り、更にポイント付与されるケースも散見されており、アンケートでは家電量販店側はこの点を指摘している会社が多かったです。
消費者側がメリットと感じる点(複数回答)は、「店舗ごとに価格を比較しなくて済む」が42%で最多で、「値引き交渉する手間がなくなる」(21%)、「購入後の値下がりを気にしなくて済む」(19%)が続きました。
逆に「メリットは感じない」とした人が41%もいて、全体としては否定的な意見が多かったです。デメリットに感じる点(複数回答)では「ポイント付与がない」(47%)で最多となり、「価格が高止まりする」(46%)、「値引き交渉が出来ない」(37%)と続き、実質的に価格が高止まりしていると感じている人が多いです。
メーカーや家電量販店は制度の説明を消費者に徹底することも課題となりそうで、制度対象商品を「買ったことがある」と答えた人は僅か3%で、「買った商品が制度対象商品かどうか分からない」は66%にも達しました。
1月にパナソニックの高級ドライヤーを購入した都内の女性は、商品が制度対象商品だったと後から気付き、「ポイントも付与されたと勘違いしていた」とした上で、価格はどこでも同じと知らず複数店舗を見て回って購入していました。
制度が認知されていない上に、消費者への説明が徹底されていない典型的な例です。これではメリットはなく不満しか生じません。価格設定も課題で「かなり高い」(24%)や「やや高い」(45%)と感じた人が多く、「妥当」と感じた人は24%にとどまりました。
これまでのメーカー側は、消費者側が望まないような新機能を付加したマイナーチェンジの新製品を毎年のように出して、価格の下落を防ごうとメーカー側は頻繁にマイナーチェンジの新製品を出していました。そうした悪循環とも言える業界構造を根本的に変えることで、健全な業界の発展を目指すことが家電指定価格制度の真の狙いです。単にメーカー側が値崩れを防止するだけの制度ではないようですが、それでも商品価格が高いと感じている現状では消費者側としては制度としての満足度は低いです。
今後、導入を検討している他のメーカーもあるようです。家電量販店は売れ残った商品をメーカーに返品出来るので、独占禁止法にも抵触しないようですが、メーカーは消費者側や家電量販店側の不満の声にも対応して欲しいところです。現状ではパナソニック社長が発言した「三方良し」ではなさそうです。

株式会社アドワン・ホーム 代表取締役
古田 晋一
宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®︎認定者
新卒で入社した総合不動産賃貸業者にて賃貸仲介・管理業務等に従事したのち、住友林業ホームサービス株式会社にて不動産売買仲介を経験。
営業時代に最優秀個人売上賞(全社1位)をはじめとして住友林業グループ表彰(年間全社3位以内)を複数回に渡り受賞。店長・支店長時代には店舗損益予算達成率 全社1位、営業部長時代には部門損益予算達成率 全社1位を獲得するなど、各ステージで特別表彰を受賞。
住まい
種別
最新記事
ONLINE meeting
オンライン相談
遠方の方やお時間の都合が合わせにくい方は
オンラインでのご相談も可能です。
お問い合わせフォームから希望の日時とご相談内容をお知らせください。
オンライン相談の流れは予約完了後のご案内メールにてお送りいたします。
ご希望の方は、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
首都圏エリア限定
個別相談会
自宅や職場などご都合の良い場所から、ビデオ通話を使用して、物件の購入・売却・賃貸はもちろん管理・投資・相続など不動産に関わることは何でもご相談できます。
CONTACT US
お問い合わせ
質問やご相談がある方は
こちらからお問い合わせください。